ブログ読者の皆様、こんにちは。今年の夏の甲子園を見てふと思う事があり、本日は身体の動きと構造についての記事を書こうと思います。
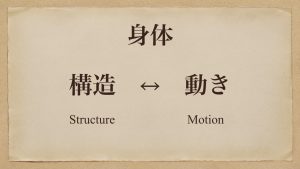
さて、人の身体の動きはその構造に必ず影響を受けます。例えば、骨盤にある臼蓋と呼ばれる大腿骨の受け皿が浅ければ、骨盤は前傾しがちです。関節を包む関節包という結合組織がとても柔らかければ、身体の各関節は大きな可動域を有する傾向にあります。この様に、人の身体の動きはその構造に必ず影響を受けます。
身体の構造的特徴は人それぞれですが、どの様な特徴にも有利な点と不利な点が大概は同時に存在します。例えば、背が高い人は高い所に手を伸ばす事には有利な一方で、身体を起こすのには大きなエネルギーが必要になります。体重が軽い人は身体を動かすのが楽な一方で、寒さに影響を受けやすくます。この様に、身体の構造的特徴には有利な点と不利な点が大概は同時に存在します。
今年の夏の甲子園である選手が全国的に注目されました。県岐阜商の横山温大選手です。テレビや新聞等で報道され多くの方がご存知かとは思いますが、横山選手は生まれつき示指から小指がありません。当然、手指の一部が欠損した状態で野球をする事には様々な不利があります。その中、甲子園であの様なパフォーマンスを行った背景には、本人の多大な努力があったのでしょう。
しかし、私はふと思います。生まれつき手指の一部が欠損している事は純粋な不利であり、有利な点は全くなかったのでしょうか?誤解を恐れずに言うならば、ある点においては手指の一部を欠損している事が有利に働いたと私は思います。
甲子園での横山選手の打席の映像(バーチャル高校野球の準決勝の第一打席)を見る限り、彼は左の手の平でバットを包む様に持っています。専門用語で書くならば、手部の内在筋を働かせ、手根骨や中手骨をしっかり動かしバットを把持しています。
横山選手の持ち方では、強くバットを握り、腕の力任せにブンブンと振り回す事は困難です。左手でバットをしっかり押す必要があります。そして、左手でバットをしっかり押すためには、下肢や体幹もうまく使う必要があります。具体的に言うと、左下肢で地面をしっかり押し、重心移動した身体を右下肢でしっかり受け止め、これらの動作において地面から得られる床反力をうまく利用する必要があります。
生まれつき手指の一部を欠損しているという不利な点が、身体を動かす上での大切な部分に集中する事に繋がった(有利に働いた)という側面もあるのではないでしょうか?
私たちの身体の構造は、生まれながらその特徴はある程度決まっていて、それぞれ固有のものです。身体の構造を変えることは、一部は可能ですが、多くは不可能です。結局のところ、与えられた身体でいかにうまく動くかが重要になります。
本日の記事では、一部において個人である横山選手について書きました。この記事において書いた横山選手の動作に関する見解は、あくまで私の個人的なものです。もし、横山選手がこの記事を読み不快な思いをされた場合は、謝罪しこの記事を削除いたします。私個人としては、与えられた身体でいかにうまく動くかを体現している横山選手を尊敬します。
関連記事
次の記事 身体の柔軟性を高めるためには何が必要か?
前の記事 ワークショップ開催のお知らせ-01