前回までのブログで紹介した動きの評価方法はセラピストの感性が重要です。なぜなら、動きの滑らかさやエネルギー効率を具体的な数字で表す(何らかの機器で測定する)事が困難だからです。「具体的な数字で表す事が困難」と書くと、「それは科学的ではない」と批判されそうです。実際私は、そう言われた事があります。果たして私の動きの評価方法は科学的ではないのでしょうか?本日のブログでは「科学的とは」をテーマに、私の動きの評価方法の特徴をご紹介したいと思います。
「数字で表す事ができなければ科学的ではない」、これは実習に来ていた学生から言われた言葉です。正確にこの言葉だったかは覚えていませんが、基本的にはそういった内容の言葉です。どうやらこの実習生は学校でその様に教わっていた様です。
科学的とはどう言うことでしょうか?これを理解するためには先人の知恵に頼るのがいいでしょう。「科学の方法」という本があります。1958年が初刷の名著です。これまでのブログで何度か登場した神奈川の先生が紹介してくれた本です。
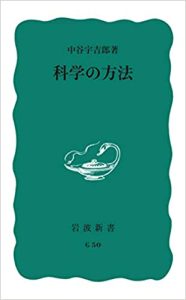
この本には「まず第一に、一番重大な点をあげれば、科学は再現可能な問題、英語でリプロデューシブルといわれている問題が、その対象となっている」と書かれています。この文章を解釈すると、科学的であるためには再現性がある事が最も重要である、と言えます。「再現性」とは、ある人と同じ事を他の人が実施した場合に同じ現象が起こるという性質の事です。例えば立位で手に持ったリンゴを離した場合、それを実施したのがアイザック・ニュートンであっても他の誰であっても、リンゴは下に落下します。誰がやっても同じ事が起こる、この性質が再現性であり、科学的であるために最も重要な点です。

この本には他にも色々と重要な事が書かれています。「数値であらわされるということが大切」、「測定によって得られた数字が自然の実態をあらわしていないか、あるいは実態のうちごく一部の性質しかあらわしていない場合は科学的の価値は少ない」、「われわれの感覚のうちのどれかにつかまえられればそれでよい」、これらの記述が印象的でした。
私は、科学的であるためには、以下の3つの要件が満たされている事が重要であると考えています。
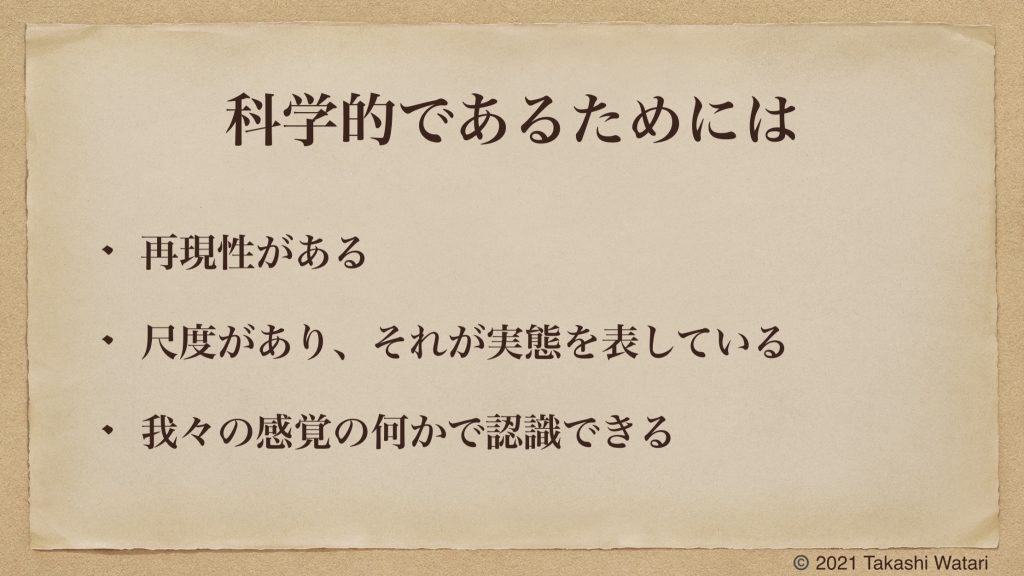
私の動きの評価方法を検証してみましょう。
- 再現性がある
私の動きの評価方法に再現性はあるのでしょうか?結論から述べると、部分的にはイエス、部分的にはノーです。(この時点で「科学的とちゃうやん?」と言われそうです・・)例えば、触診の中で異常な抵抗を感じる部位には動きの制限がある、この現象には再現性があると思います。また、余分な抵抗が少なくなればその分だけ動きは滑らかになる、外力をうまく使った動きには身体の弾性(バネ)や腹部深層の適度な筋活動が感じられる、これらの現象にも再現性があると思います。しかし、ある患者さんに対して複数のセラピストが評価をした際に全員が同じ結論に至るとは思いません。例えば、セラピスト全員が同じ部位の動きの制限を認識するとは思いません。なぜなら、人の感性は個々に異なるからです。
私の動きの評価方法の特徴は、1人のセラピストが複数の患者さんに対して評価を実施した際に、そのセラピストの感性に基づき再現性のある評価ができる一方で、複数のセラピストが1人の患者さんに対して評価を実施した際には、各セラピストの感性は異なるため再現性のある評価ができるとは限らない、という事です。これを専門的な言葉で言うと、「評価の検者内信頼性はあるが検者間信頼性は乏しい」となります。(今日も硬いブログになってしまった・・、一般の方は軽く読み流して下さい・・)
- 尺度があり、それが実態を表している
尺度とは、物事を評価する際の基準です。例えば、人の体重を測る際には「Kg重」という尺度が一般的に使わます。尺度は、その特徴により名義尺度・順序尺度・間隔尺度・比例尺度に分けられます。例えば、「Kg重」という尺度はゼロという数字に絶対的な意味があり比例尺度に分類されます。気温や西暦は間隔尺度、人気ランキングやテストの成績を数値化したものは順序尺度です。
理学療法領域では関節可動域(ROM)や徒手筋力検査(MMT)が動きを評価するための有名な尺度です。ROMは比例尺度、MMTは順序尺度に分類されます。滑らかさとエネルギー効率は比例尺度です。
滑らかさとエネルギー効率という尺度は、実態を表しているのでしょうか?ここで言う実態とは、例えば歩行時に膝が痛いなど、患者さんが有する様々な身体的問題を指すでしょう。
以前のブログでも述べましたが、滑らかさとエネルギー効率という観点は患者さんの言葉に基づくものです。つまり、患者さんが「楽です」・「軽いです」・「痛くないです」この様な言葉を言った際にどの様な変化が身体の中で生じているのかをみる過程の中でたどり着いた観点です。そのためこれらの観点は、動きをみる尺度として有用である、別の言い方をすると、患者さんが感じている実態を表している尺度であると思います。
- 我々の感覚の何かで認識できる
このブログにおいて動きの滑らかさとエネルギー効率という観点には明確な定義があります。そのため、数値で表す事が理論上は可能です(詳しくはこちらとこちらの記事を参考にして下さい)。しかし、現状ではそれは困難です。なぜなら、それらを測定できる機器がないからです。とはいえ滑らかさとエネルギー効率の評価は、動きに関与する「力の作用」を感じる事で実施可能です。力の作用は我々が認識する事が可能な感覚です。
この社会では、様々な場面で人の感覚が役に立ちます。例えば、橋やトンネルをメンテナンスする人は、打診棒と呼ばれる器具を用いて構造の検査を実施します。この時、「音」の感覚を利用します。パン職人やうどん職人は、手に伝わる感触を基に生地の状態を把握するでしょう。動きの滑らかさとエネルギー効率の評価もそれらと同じです。手や目から得られる感覚を基に評価を実施する事が可能であり、それで十分ではないでしょうか。
これは余談ですが、レシピ通りの料理を作るのは簡単です。しかし、職人として一歩その先に進むには、自分の感性を信じて試行錯誤を繰り返す事が大切ではないかと思います。
以上、検証は終わりです。私の動きの評価方法が科学的であるか否か、読者の皆様の判断にお任せします。ところで、私の動きの評価方法は、物理の原則に基づき患者さん個別の状況を把握する、という特徴があります。普遍的な原則に基づき個別の状況を把握する、この様な推論過程を「演繹法(えんえきほう)」と言います。演繹法の反対に「帰納法(きのうほう)」と呼ばれる推論過程があります。様々な事例を基に一般的傾向を導く、これが帰納法の特徴です。一般的に多くの研究は、帰納法による推論がなされます。そしてそれにより得られた知見が科学的根拠として使われています。
理学療法の現場では、研究により得られた様々な知見も重要ですが、患者さん個別の状況に迫るには演繹的な推論も必要ではないかと思います。なぜこの様な事を書くのかというと、「研究に基づく根拠があれば科学的」、「それが無ければ科学的ではない」という考えには疑問があるからです。
本日のブログでは、「科学的とは」をテーマに私の動きの評価方法の特徴をご紹介致しました。今日の内容は完全に専門家向けでした。基本的に私のブログは一般の方向けにも書いています、本当です・・。実際、私の患者さんにも読んで頂いていると思います。読者の皆様、今日の内容はヘビーですみません、あっ物理的な意味ではなく・・。
さて、次回のブログから、ようやく身体の動きを良くするための具体的な内容に入ります。次回のブログは今日よりもきっと読みやすいはず・・。それでは、また次回。
関連記事
前の記事 良い動きとは何か?-15-【触診】